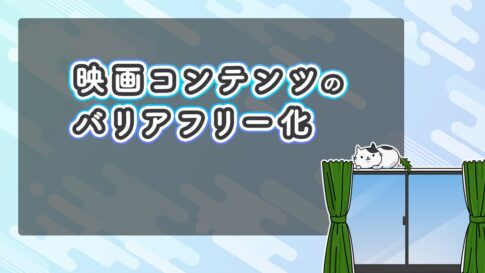デジタルシネマパッケージは、DCP(ディーシーピー)とも呼ばれており、それは、厳格なデータ構成で制作(マスタリング)されたデジタルデータによる「劇場上映での投影方式」です。
映画館では現在、フィルムでの映写上映にとって変わり、ほぼ全ての上映システムでDCPによるデジタルデータ上映方式に切り替わって運用されているフォーマットです。
DCPとは?
現在、適正な解像度で出力された映像と音声があれば、デジタルシネマパッケージはフリーソフトでも作成でき、マスタリング制作まで可能です。
無料のソフトでも作ることが出来るようになったデジタルシネマパッケージは、制作環境が整っているので、DCPの解像度やフレームレートに関連した規格を把握しておけば、制作進行が可能な技術です。
フィルム上映からDCPへ
現在、映画を公開するほぼ全ての劇場で、フィルム上映からDCP上映へ切り替わっています。
DCPのデータ構造自体は複雑なものです。
しかし、DCPマスタリングをする技術者以外は、最低限のフォーマット情報を覚えおけば問題なく業務を進めることが可能です。
- DCPってそもそもどういうデータなの?
- DCPの技術情報がやっと増えてきた!
- DCPで使用されている解像度
- DCPで使用されているオーディオスペック
- DCPのフレームレート
- DCPはちょっと特殊なカラースペース
それでは、DCPの解説をしていきます。
①DCPってそもそもどういうデータなの?
DCPとは、映像データ、音声データ、字幕ファイル、コンテンツの権利情報ファイル、再生制御など、デジタルシネマパッケージの構造は、多くのファイルで構成された「ファイル構成」そのものを指します。
構成された各ファイルは、ひとつの時もあれば複数で複雑に構成・管理されています。
これらは、複雑なデータ構造で構成されたデータを上映するために必要な構成リスト(CPL)や、コンテンツを劇場で使用するサーバーにデータ移動(インジェスト)する際にデータが破損されていないかをチェックするための要素となるPKL(Packing List)などが格納されています。
このように様々なデータ形式が1つのパッケージに格納できるため、映画上映でのバリアフリーコンテンツ制作においても活用されています。
構成要素として、それ以外にもアセットマップ(ASSETMAP)やボリュームインデックス(VOLINDEX)、またコンテンツを安全に劇場公開までに運用できるようにデータをセキュアな状態にするためのKDMなどが格納されています。
②DCPの技術情報がやっと増えてきた!
いきなりDCP制作にチャレンジしてみようと考えると、以前はWeb上の日本語ソースではWeb上にほとんど情報が上がっていませんでした。
現在では情報量も多くなり、DCPの技術情報を共有化される方が増えてきたおかげでDCP制作の障壁も少なくなってきています。
また、有償ではありますがeasyDCPの操作性が良くなり、DCPマスタリングをするテクニカルな部分の作業も簡単になってきています。
現在では更にIMF Studioシリーズも展開され、IMF CreatorとIMF Playerも揃っているので、手軽に最新アーカイブフォーマットを作れる用にもなりました。
easyDCPはアップデートに関してサブスクリプション型の料金モデルなのでちょっと費用が掛かりますが、現在は1本だけ利用の料金ラインナップなども対応しているので、是非、DCP制作をするときには検討してみてください。
③DCPで使用されている解像度
まずは、DCPがどのようなレベルの解像度で上映されているかを知りましょう。
DCPで使用されている解像度は
- HDTV (1920 × 1080 or 3840 × 2160)
- Flat (1998 × 1080 or 3996 × 2160)
- Scope (2048 × 858 or 4096 × 1716)
- Full (2048 × 1080 or 4096 × 2160)
などがあります。
ただ、予告編なども含め、データの解像度と上映される本編が持っている解像度やアスペクト比は、一致しないこともあります。
④DCPで使用されているオーディオスペック
DCPで使用されている音声は基本的にリニアPCMの 48Khz・96Khzの24bitで格納されます。
ただ、リニアPCM以外にもいくつかの音声フォーマットが使用されており、現在はかなりの高音質を劇場で楽しむことができます。
⑤DCPのフレームレート
DCPのフレームレートは基本的には24pになっていますが、ODS(Other Digital Stuff)の場合には30fpsになっている物があります。
⑥DCPはちょっと特殊なカラースペース
デジタルシネマパッケージのカラースペースはXYZの色空間で指定されています。
制作進行業務でDCPでのコンテンツ運用を任された場合、一番最初に確認すべきポイントは、映像はJPEG2000 12bit XYZカラースペースで格納されているということを忘れないようにしましょう。
XYZのカラースペースでQCを行うときは、ソフトによって設定がバラバラです。
最近は、ソフトウェアで簡単にDCPマスタリングが出来ることもあり、素材(DCDM)をDCP用にJPEG2000エンコードした際に、XYZカラースペースに変換されていることを知らないエンジニア担当の方も出てきたのでご注意ください。
カラースペースの変換がどのように影響するのか、DCPに変換するときはカラーバー使って色がどのように変わるのか実際に目で見てみて検証しておくと学びになります。
DCP制作に向けて
DCPのデータのことを知ってもらった中で、次はDCPの制作進行業務に向けてどのような準備をすれば良いのか解説していきます。
- DCPマスターデータはどう用意すればいいの?
- 入稿時によくある映像フレームレートのミス
- データのフォーマットチェックツール
①DCPマスターデータはどう用意すればいいの?
DCPマスタリングされたデータはとても複雑なデータ構造ではありますが、必要なコンテンツデータは放送用やパッケージコンテンツ(DVD/Blu-ray/UHD Blu-ray)、配信用に用意するマスターデータとさほど変わりません。
DCPにするために重要なことは、DCPマスタリングする前のコンテンツのフレームレートを24pか30pにしておき、音声データをリニアPCM 48Khz・96Khzの24bitで用意することくらいです。
②入稿時によくある映像フレームレートのミス
よくあるトラブルとして映像マスターのフレームレートで、DCPに適したフレームレートになっていないことがよくあります。
24p(23.976PsFや23.98PsF)、 30p(29.97fps)が同一な方がいらっしゃるのですが、厳密には全く違うフレームレートなので、ここで24pは完全な24pで納品をするようにしてくだい。
この辺りは、コンテンツ制作担当者の方とクリエイター、エンジニアの間で、認識や会話のズレが結構多いので、まずはDCPにしようとするコンテンツが、変換のための正しいフレームレートでコンテンツの準備ができているかを確認しましょう。
③データのフォーマットチェックツール
データの中身(フォーマット)チェックには、Media Infoというツールが活用できます。
自分で24pにしたつもりでも、ソフトによっては24p(23.976PsF)で結局出力されていたということもよくあります。
また、納品データがOS環境によって、そもそもデータの確認ができないという方もいらっしゃいます。
とはいえ最近は、OS間で都合が悪い出力フォーマットも、コーデック(ProResやカノープスコーデックなどの特殊なデータを再生するためのデータ)が揃う環境になってきました。
これらのツールでDCP環境を整備してDCP制作進行に役立ててください。
DCP(デジタルシネマパッケージ)の情報まとめ
このユニコブログ®︎では、筆者自身が多くの映像製作会社でデジタルシネマパッケージ事業を立ち上げてきた経験をブログ記事として書いています。
現在、映像技術関連の顧問をしながら新しいフォーマットについても事業化して運用したりしています。
映画館でデジタル上映するために必要なデジタルシネマパッケージ制作事業を開始しました。『合同会社ユメキラメク:PR TIMES より』
本記事以外にもDCPに関連した内容をまとめた、多くの記事を作成しています。
実際の経験から得た、デジタルシネマパッケージに関する様々な情報が確認できますので、これらの記事がお役に立てば幸いです。