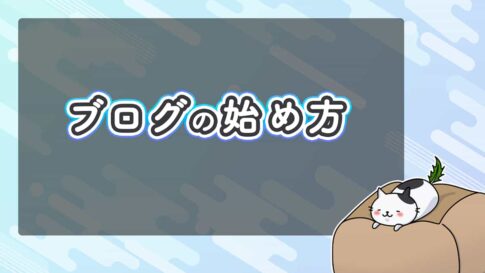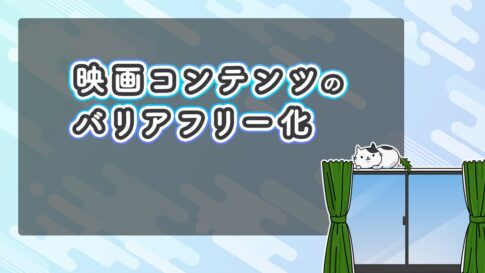デジタルシネマパッケージにおいては現在、いわゆる、普通のスペックと言われる様なPCさえあれば、追加の費用をかけずに自分で作成することが可能です。
実際に、筆者が起業したばかりの時、DCPマスタリングには、2020年製の一般的に販売されているスペックのPCを使って制作していました。
特に、予告編などの尺の短い制作物については作業負荷が少ないため、DCPへの変換は手軽に無料で利用できるアプリケーションを利用していたこともあります。
DCPは、無料のツールでも映画館で問題なく再生できるほどの制作環境が揃っているので、本記事がお役に立てば幸いです。
- DCP制作は簡単になった
- 費用をかけずにDCPは作れる
- DCPの制作や再生環境の紹介
デジタルシネマパッケージの意味
デジタルシネマパッケージ(digital cinema package)は、略称でDCPと称されています。
映画館で利用されていた35mmフィルムに代わり、デジタルデータでの上映を目的として作られた映画コンテンツを格納しているデータフォーマットの事です。
- DCPの構成要素
- DCPで使用される画像のフォーマット
- DCPで使用されるオーディオフォーマット
DCPの構成要素
MXFでラップされた、少なくとも最低2つのファイルで構成されています。
MXFでラップされている最小限のファイルは、ムービーデータとオーディオファイルです。
この他、再生シーケンス情報として提供されるコンポじっションプレイリストなどがXMLで構成されています。
DCPで使用される画像のフォーマット
DCPはJPEG2000フォーマットにより、連番で構成された画像ファイルの連番再生により映像を表現しています。
カラースペースがXYZカラースペースという、通常よくあるRGBではない点に注意です。
DCPで使用されるオーディオフォーマット
オーディオファイルは、48khz、または96khzのサンプリングレートが使用されます。
量子化ビット数は24bitです。
最大16チャンネルの独立した音源を利用可能です。
DCPの容量
DCPは、マスタリング際の圧縮結果として、おおよそ200GB以上250GB未満で作成するように設定されます。
圧縮後の結果は、映画の内容によって100GBくらいまで圧縮できてしまうものなので、データ容量が設定より小さくなってもあまり心配はありません。
また、250GBギリギリの容量に敢えて設定することも出来ますが、シネマサーバーによってはインジェストエラーになるので、圧縮後の容量を設定できるソフトを使用する場合には、230GBくらいをMAXにしておくのが無難です。
納期があまりに短くて、DCPのコピー本数が多かった時に納品したら
「圧縮率を高くしているのでは?」
なんていう質問もかつてはありましたが、DCP制作を請け負う側として、黙ってそういうことはしないと思います。
DCP制作の料金
DCPを格納するのに使用するメディア代金は別ですが概ね
- 個人に頼むと5万円〜10万円
- 中堅どころで10万円〜15万円
- 大手スタジオで20万円〜
くらいになります。
価格はDCPマスタリングだけの値段です。
今後は、営業窓口も引き継いでいきますが、筆者も以前はDCPラインを2ライン持っていて、DCPマスタリングを行っていました。
現在は、映画製作や映像加工で事業化したいという人がいたので、起業のサポートを含めてDCPマスタリングのノウハウを提供し、2021年03月には独立した形で起業をしてもらえました。
関連リンク:DCP制作【デジタルシネマパッケージ】|価格感付きの参考サイト : 編集後記ブログ
筆者が設定している価格は、HDDやUSB込みで5万円(120分前後)くらいとかなり安いのですが、本来、実際の流れで重要なカラーグレーディングとDCPマスタリングはセットでおこなった方が色の品質管理が可能なので、予算によって判断が必要です。
また、DCPマスタリングだけの制作をお願いすると、お願いするところによっては映像尺やオーディオチャンネル数で各社、価格が大きく変わります。
デジタルシネマパッケージの作り方
そんな中、デジタルシネマパッケージの作り方はとてもシンプルになりました。
下記に、具体的な手順の実例を紹介します。
- OpenDCPを入手する
- 映像素材を24Pに整える
- 音声素材を24bit/96khzに整える
- OpenDCPで変換する
- DCP-o-matic PlayerでQCを行う
これだけで完成させることができます。
デジタルシネマパッケージとは?
デジタルシネマパッケージの基本的なことは、こちらの記事でも紹介をしています。
数年前のDCP制作事情
DCPは2016年頃まで、本編の編集を終えてからDCP化するのに作品一本あたり数十万円から百万円近くするような物でした。
当時、日本の映画監督の方々は、このDCPマスタリングの予算が製作予算に大きく影響する悩みを抱えていました。
DCPの実演公演
そんな中、日本の映画作品をもっと世界に発信して活性化できたらとの願いを込めて、試行錯誤をしては様々な施策を行っていました。
2016年02月に、当時では珍しかったDCPデータをプロジェクターベースではなく、普通のテレビで試写を行えるようなシステムを構築しました。
また、DaVinci Resolve(無料版でも十分にフィニッシュまでもっていけるスゴイ編集ソフトです。)をベースにしたDCP化する前のデータの整え方から、自分でDCPに変換する方法までを劇場で講演する機会をいただきました。
実際の劇場でDCPを制作しながら上映までをその場でやるという、おそらく、世界初?日本初?のようなことを経験できたことは、とても貴重なことでした。
費用をかけずにDCPを制作する環境
続いて、編集パートまで完成した映像作品を、費用をかけずにDCPに変換する方法にうつります。
利用するアプリケーションは2種類あります。
今回は主の2つのソフトを紹介します。
上記の2つのソフトは無償でコンテンツデータをDCPに変換できるソフトです。
OpenDCPについては、下記の記事で制作方法を紹介しています。
また、DCP-o-maticについての詳細なDCPマスタリングの方法については、別の記事で書かせていただきます。
まず、DCPを作成してみるにはOpenDCPを使用した方が早く多くの知見を得ることができます。
いちばんの課題だったDCPの再生環境
その他にも様々なパッケージソフトがありますが、今回の記事でお伝えしたかったのは、少し前まではDCPを制作した後の再生チェックできる環境は、無償版ではなかったのです。
「DCPを作成した/DCPの納品をしてもらった」としてもそれを簡単にチェックすることができませんでした。
そのために、確認用にわざわざ変換したデータをまたQC用に戻して(解像度変換したりしているため)DCP変換後に再度チェックをやったりしてまた修正!!など、双方にとって余計な作業が発生したりしていました。
DCPは無料のプレイヤーで再生できるようになった
今では、無料で利用できるDCP-o-matic Playerなどを用いてDCP内のプレイリストをを再生できるようになりました。
変換が完了したDCPデータをこのソフトプレイヤーにセットすれば、QC(Quality Check)が可能となります。
この辺りは、映画の予告編レベルなどの場合だと、自分で再生環境を構築してチェックしたい作品進行担当者にとって需要が多い部分ではないでしょうか。
DCPの納品フォーマット
QCを自分の所で行うには、予告編レベルの物であればセキュアなファイル転送でDCPデータを送ってもらってもいいし、USBをFAT32でフォーマットしてもらって受け取れば、Linux環境でなくとも簡単にDCPデータを扱うことができます。
予告編レベルの小さいデータはFAT32のフォーマット環境でも納品ができるのでDCP-o-matic Playerで最終的なQCを自分のPC環境で行うこともできます。
劇場にDCPを納品する
DCPは、劇場への納品形態にも変化が起きています。以前はDCP Kitという、大きなケースにCRUカバーを添付して、HDDと合わせて納品する形式が一般的でした。
現在は一般的に購入できるHDDでも受け付けてもらえるようになりました。
DCPをUSBで納品する
DCPは、USBに格納して劇場に納品することが可能です。
現在、USBは大容量化されて本体の値段もかなり安価になりました。
本編データを納品する場合にはUSBをextフォーマットにする必要がありますが、予告編レベルであればUSBをFAT32のまま運用することが可能です。
USBは大容量でもかなり安くなったので、今後もUSBでの運用が増えていきそうですね。
DCPをHDDで納品する
少し前までは、DCPはCRUカバーを添付して劇場に納品するのが普通でしたが、現在は一般販売されているHDD製品でも受け付けてくれるようになっています。
劇場へのDCP納品は本編データの容量の場合はLinuxのフォーマット(ext)で進行するので通常はなかなかデータを簡単に取り扱うことができません。
DCP(デジタルシネマパッケージ)の情報まとめ
DCP関連の内容をまとめた記事を作成しました。
こちらの記事を読んでいただければ、デジタルシネマパッケージに関する様々な情報が確認できます。
デジタルシネマパッケージの情報をブログで書いていく
この記事を読んでいる方は、ほとんどの方が放送・映画業界に従事している方だと思います。
映像技術関連の中でも、デジタルシネマパッケージについて書かれた日本語の情報は少なく、映像制作分野でも、このあたりのプロセスに関する情報をまとめたブログサイトは、ノウハウ共有によって大きく収益化できる可能性があります。
- ブログサイトから直接案件を集客する
- ブログサイトにアフィリエイト広告を貼る
- Googleアドセンスを運用する
- デジタルシネマセミナーなどの開催
- 技術オンラインサロンの同時開設
DCP(デジタルシネマパッケージ)というテーマでも、充分に集客や収益化は可能で、ブログの育ち具合によっては映像制作に関する集客に役立てることで、筆者の様に独立することが可能です。
若干話がそれますが、筆者の三男(開設当時は小学4年生)も自分でブログを立ち上げましたが、現在はそれくらいブログが簡単に解説できるようになっています。
また、これはスゴく重要で、ブログは会社ではなく絶対に自分のブログとして立ち上げてください。
独立したりするときに、自分で積み上げたコンテンツには集客力があります。
自分の物としてWebサイトやブログを所有しておかないと独立してから結構苦労します。
何でもかんでも独立を推奨しているわけではないのですが、何かと課題の多い業界でもあるのは既にご存知だと思うので、せめて独立時の集客メディアは最低でも1つは持っているとスタートが随分と違います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。