Google検索セントラルからAI生成コンテンツに関するガイダンスが公開されています。
本記事の執筆時点(2023年02月09日時点)では英語になっていますが、おそらく、いつも通り、日本語版のガイダンスも提供されると考えています。
ただ、英語文献でも、今はブラウザから簡単に英語から日本語に翻訳してサイトコンテンツが読めるので、Webサイトを運営されている方は読んでおくとスゴく役立つと考えています。
AI生成コンテンツの利用でGoogleからペナルティを受けるのか?

今回のGoogle検索セントラル内に、AI生成コンテンツに関するペナルティについては下記の内容が記載されています。
Why doesn’t Google Search ban AI content?
※訳:なぜGoogle検索はAIコンテンツを禁止しないのか?Automation has long been used in publishing to create useful content. AI can assist with and generate useful content in exciting new ways.
Why doesn’t Google Search ban AI content?|Google検索セントラル
つまり、AIによるコンテンツの生成は、これまでも有用なコンテンツの制作に役立っていると考えられています。
ただ、別の見出しで下記のようにも書かれています。
Should I use AI to generate content?
※訳:AIを使ってコンテンツを生成するほうがいいのか?If you see AI as an essential way to help you produce content that is helpful and original, it might be useful to consider. If you see AI as an inexpensive, easy way to game search engine rankings, then no.
Should I use AI to generate content?|Google検索セントラル
AIによるコンテンツ生成がオリジナリティに富んでいて、有用なコンテンツであれば良いが、単に検索エンジンのランキング操作に利用するだけなら「NO」だとも記載されています。
従って、筆者の受け取り方としては、AI生成コンテンツの利用自体は問題ないが、単にAIに生成させた情報だけのコンテンツを作っていくのはダメだな…。という感じです。
あくまでも、コンテンツ制作の補助ツールとして利用していくのが良いかも知れません。
AI生成コンテンツはGoogleのガイダンスを理解して利用する
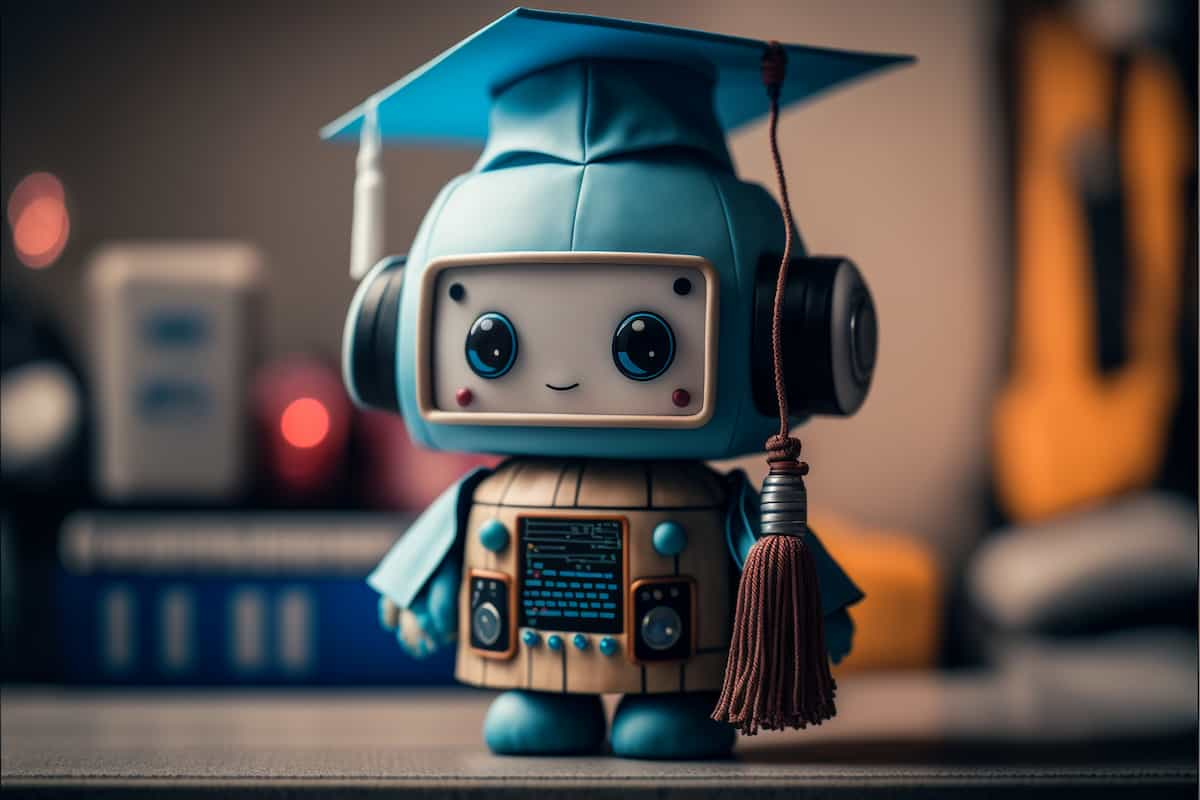
最近、ChatGPTの使い方についてブログ記事を書きました。
新しいテクノロジーは、実際に体験するのが1番です。
これは、筆者自身が空中ディスプレイを含む、新しい技術についての事業立ち上げを、続けてきた背景があるからなのですが、やはり、こういうモノは実際に使ってみるのが1番と考えています。
AIのコンテンツ生成機能を搭載した検索エンジンを体験する
また、2023年02月08日には、検索エンジンのBingがOpenAIの大規模言語モデル(LLM)を実装した検索フォームに更新され、大きく話題となりました。
参考リンク:Bing検索フォーム
実際に、Bing検索フォームで筆者も検索を試してみました。
検索サービスが違うとは言え、AIによるチャット検索や新しい検索機能は学びになります。
最初は短い文で質問していって、段々と具体的な質問を入力していきます。
その検索結果や、AIチャットが返してくる返事から読み取れる情報はスゴく大きいです。
いくつか気付くことに、AIによる回答には、自身の経験や体験などによるコンテンツが入っていないことが分かると思います。
また、検索意図の背景なども含めて、より的確にAIから回答をもらうには、多くの情報を入力する必要があります。
経験や実体験に基づいたオリジナルコンテンツの制作

そんなことからも、コンテンツ制作に関して大事なE-A-Tの要素が、更に「Experience の E 」を追加したE-E-A-Tになりました。
コンテンツ制作者の体験や経験がどれくらい盛り込まれているかも、今後は、より重要になってきます。
でも、これは今までとあまり変わらない部分で、コンテンツにオリジナリティーを出すには、自分の体験や経験、実際に何かを利用した、作ってみた、などの内容がないと、他のサイトコンテンツと被ってしまいます。
なので、この部分についてはAIによるコンテンツ生成について、あまり意識する必要はないかも知れません。
普遍的な情報の部分を取り纏めるのには向いている
Webサイトが取り扱うテーマやジャンルによっては、メインのコンテンツ内に普遍的な情報を入れる必要がある部分が出てきます。
そんな時に、AIコンテンツ生成ツールやサービスを用いて、すぐにまとめてもらうために補助ツールとして利用が出来るかも知れません。
筆者の場合は、実際にChatGPTを用いて、どんなコンテンツをまとめるのが得意で、何か不得意なのか、色々と試しています。
AIが生成したコンテンツには入念な検査や確認が必要
AIが生成するコンテンツの精度について、色々なサービスを試していますが、AIは、まるでそれが完全に正しい内容のように、間違った情報を生成することをあります。
現在、有名どころではGoogleのLaMDAを活用した会話型AIの「Bard」、OpenAIが提供している「ChatGPT」などの名称がよく出てきていますが、ほかの企業からも独自のAIコンテンツ生成を可能にしたサービスが出てきています。
全てのサービスを試した訳ではないのですが、人間による内容の正確性チェックは必ず行わなければいけないと考えています。
(人が書いたモノでも、チェックする必要があります…。ので同じことなのかも。)
なので、筆者の場合は、正確性や内容のチェックが簡単な部分だけに絞って、AI生成コンテンツを利用する用に作成した検証サイトで下記の3つを試しています。
参考ツイート:OpenAIの技術について|@ReonaKobayashi
当時、ブログ記事のテキストを解析して適切なディスクリプションを生成してくれるプラグインを作ってみました。
- メインコンテンツを読み込んでタイトルとメタディスクリプションを生成してみる
- 構造化データ作成の補助
- アイデア出しをするときの補助ツール
AI生成コンテンツを利用した時のルールなどが出来てくる?

現在も、AIによるコンテンツ生成を利用した場合には、それを開示するなど、各メディアによって独自のルールを発表しています。
それ以外にも、今後は業界ルールや法律などによって、AIによる生成コンテンツを利用した場合の表記などについてルールが出来てくるかも知れません。
しばらくは、このあたりのWebマーケティング業界におけるAIのコンテンツ生成については情報を追いかけていく必要がありそうです。
また、運営するWebサイトのテーマやジャンルによっては、AIでコンテンツを生成する必要がないコンテンツ分野もあります。
活用事例として、AIによって大規模な情報を取り纏めた上で、専門家としてオリジナルの考察を入れた高品質なコンテンツを制作していくなど、様々なコンテンツ制作プロセスを各々作り出していきながらAIコンテンツ生成の活用は進んでいくと考えられます。



