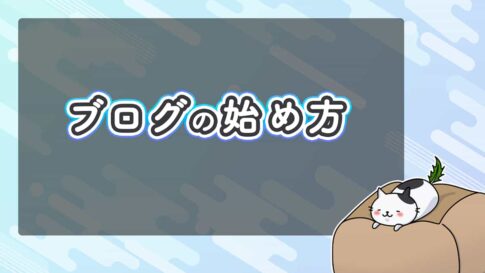今回の記事は、万能的に対応できるか?というと違っていて、環境によってはプラスには作用しないこともあります。
けれど、今でも良くある光景で、業務の内容とは別に、自己啓発というか、哲学的な内容の書籍とか、少し対応が難しい状況のジャンルを渡されることが多くあります。
組織的な付き合いの中では、この辺りの対応によって何かと不便を被る場合も多く、また、内容的にすごく深掘りされた内容であったりすると、業務時間外の自由を圧迫する可能性が高いです。
正直、この対応方法は、最初がスゴく面倒な内容です。
けれど、何回も繰り返して慣れてくると、「単に書籍を読む以上の内容に対応できるようになる。」というメリットがあります。
そんな感じなので、あくまでも一例として、そのような状況でコミュニケーションをとっていかなければいけない中でも、少しずつ効率的にこなしていける方法として書き残していきます。
基本的には当事者間の関係性が1番大事

本記事の内容は、正直、自分のためを思って、その人が読んだ書籍を端折って読み進めていく方法なので、不義理なやり方のように感じる人もいると思います。
しかしながら、特にフロント側のセールスになると、このような状況に遭遇する方も多いと思います。
特に、ある一定の年代を超えると、この辺りのやり取りは多くなると考えています。
ただ、業務内容に直結する内容の書籍や、業務をうまくこなしていくために必要な関連書籍などの場合は、社内の人が薦めてくれた書籍は大いに参考にするべきだと考えています。
自己啓発や哲学的な内容の書籍になってくると、その人の個人的な考えによって物事の捉え方や価値観に大きく関係する内容を読むことになるので、第三者的に、俯瞰的に読んでいくことができないと、正直、すごく辛いし、そして、渡された書籍を読まないことによって不条理な状況にあることも、関係性によって生まれる場合もあります。
本記事は、あくまでも、そつなく、このような状況に効率よく適応するための1つの事例として書いていきます。
書籍を渡されたら確認する必要がある重要な部分とは
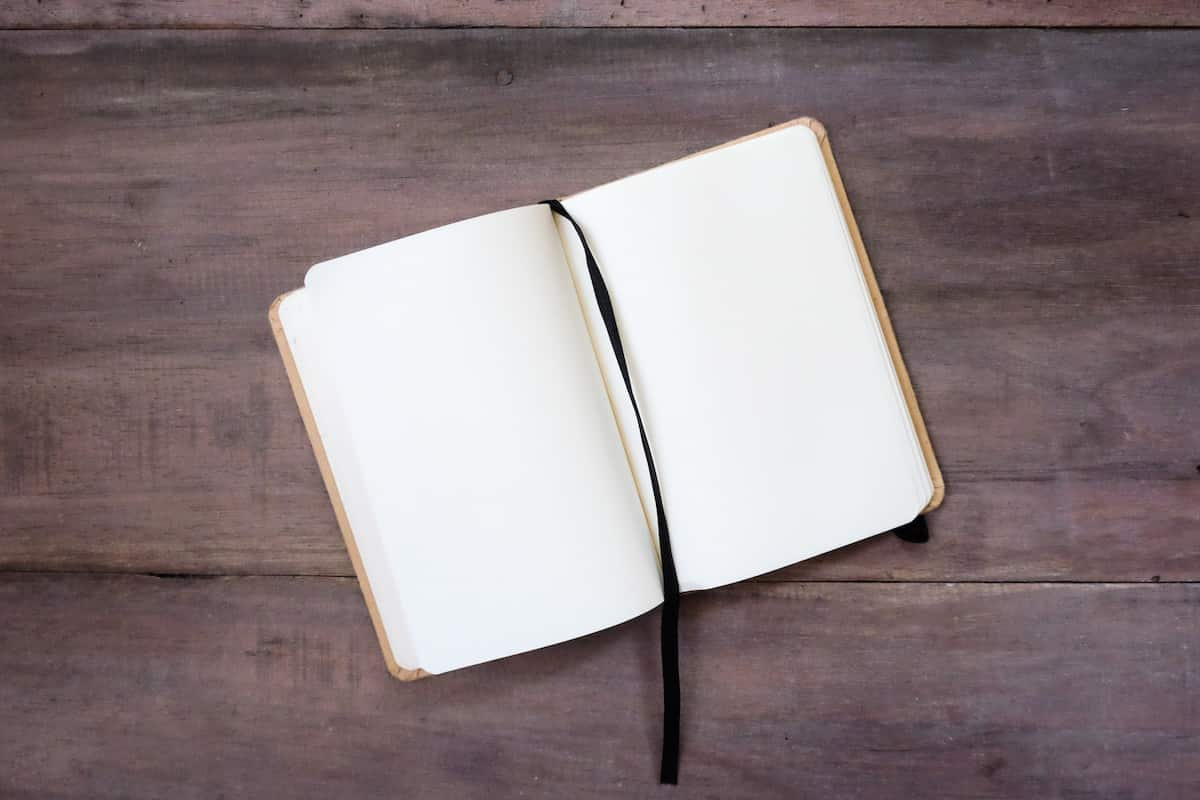
不意にお薦め書籍を渡されて、「なんか、読むこと前提…。」みたいな感じになってしまった場合、何も読まずにその書籍を返すのはなかなか難しく、かといってずっと返さないのも、つまらないコミュニケーショントラブルを生むことになります。
それらを回避するために、お薦め書籍を預かってしまった場合、書籍自体を読む前に、以下の内容に関連した情報をなるべく確認してから読む準備をします。
著者情報について
著者情報は、書籍の内容以外にも、お薦め書籍を渡してきた人の嗜好を知るための質問で大いに役立つ情報が入っています。
うまくいけば、書籍のこと以外に、その著者について話してもらう方向に持っていくことができるので、書籍の内容自体から会話のトピックをずらしていくも可能になる重要な情報になります。
お薦め書籍で渡された著者の情報は、Webで調べれば間違いなく出てくるはずです。
日本語でも英語などでも、著者情報についてWebで全く経歴や背景が出てこない場合は、その正確性について少し注意が必要になる場合があります。
また、そのような場合は、書籍で書いてある内容に対して常に意識しなければいけない部分が出てきます。
- 統計データ元(調査方法が不明で100人からしかデータを取っていない場合等)は信用できるか?
- 定量的なデータの分析に対する切り出し方が極端ではないか?
- 主観的な内容なのか客観的な内容なのか?
このほかにも、記載内容に関する引用がある場合は、そこまで調べたほうが良い状況まで出てくる可能性があります。
特に2010年代初頭から、電子書籍も含めて自費出版で書籍を流通させることがスゴく簡単になりました。
Webで著者情報がしっかりと出ているかは重要なポイントになることに留意ください。
この辺りの判断が難しい場合、更に合わせて
- 出版社
- 著者の書籍で他にどんなものがあるのか?
- 第三者に紹介されている情報で何か言及されているか?(これについては極端に良く、悪く書かれていることがあるので、内容を吟味する必要があります。)
なども重要です。
書籍の斜め読みで済ませても良いのですが、このようなことって組織で働いたりすると今だによく起きる状況なので、「読む前の調べること」について手順を知っておくことは損しません。
※ 場合によっては、上司などから「顧客の〇〇さんから預かっちゃったから、代わりに読んで、後でポイントだけ教えて!」なんていう場合も多々あります。
いつ発行された書籍なのかを確認する
特に初版(初刷)されたのがいつなのか?
これはとても重要です。
書籍のジャンルによっては、その時の時代背景を色濃く反映した内容が書かれているものが多いです。
特にエッセイや著名人の定期的な現代評論などに多いパターンです。
なので、上記の他、論文集なのか、ジャンルは何なのか?
初版で出された年月日はいつなのかを把握しましょう。
また、書籍は重版されている場合もあります。
その時、何か修正がされている場合には、その内容が添付されていたりします。
何版目なのかを知るには、書籍の最後のほう(奥付け)で記載されているので確認しましょう。
書籍の中身を確認する
お薦め書籍には、書いてあること以上に読んだ人が記録した情報が沢山詰め込まれています。
最近は、中古として売るときに書籍に何らかの加工をしていると買い取ってもらえない場合がありますが、お薦めして渡してくらいなので、大抵は何らかの情報が入っています。
- しおりのある書籍の場合はソコが最重要の内容になっている可能性が高い
- マーカーや何らかの線などが引いてある箇所を書籍全体で探してみる
- ページがおられている箇所
など、書籍に何らかの手が加えられてるところは重要なポイントになります。
これらの部分は
「その書籍を読んで重要と感じたところ」
のはずなので、ソコだけは外さないように押さえどころとしておきましょう。
お薦めされた書籍の効率的な読み方
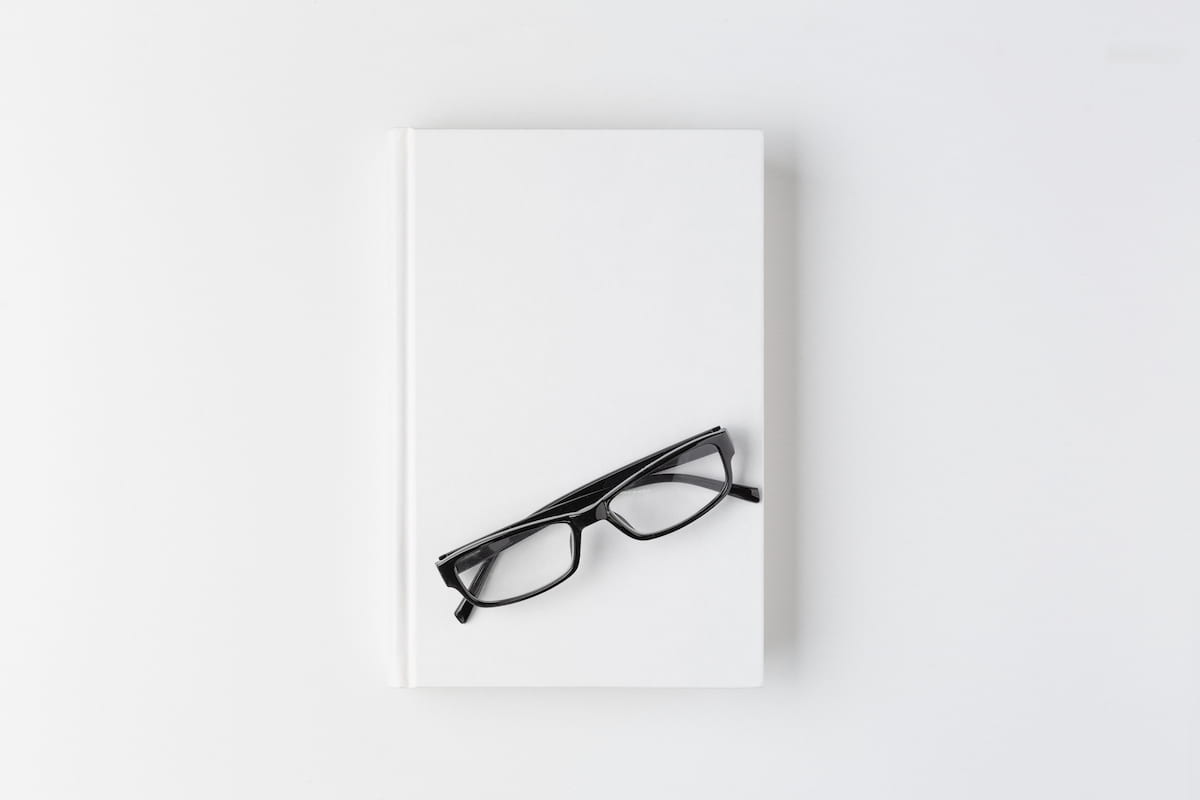
ここまで準備をした上で読み始めます。
正直、ここまでの段取りはすごく面倒ですが、単に読むよりも、ものすごく得られる情報が多くなります。
また、調べている間に関連情報として書籍の内容と繋がるので、何かと覚えやすいとメリットもあるので、読む前の準備方法として身につけてしまったほうが、結果的にメリットが大きいと考えています。
書籍を読む箇所は最初と最後と手を加えられている場所
お薦めで渡された書籍で読む箇所は3箇所です。
- 書籍の最初(まえがき)
- 書籍で手を加えられているところ
- あとがき的な所
この部分だけ読んでおけば大概は大丈夫です。
ただ、それだけでは読み取れきれない部分は、書籍の目次を確認して追いかけると効率よく書籍を読み進められます。
書籍の感想を聞かれるか聞かれないかは人によるので分からない
働くようになると、「聞かれなかったら答えなかっただけ。」と、重要になる部分を平気で言わないような人に出会うことが当たり前のようにでてきます。
そこまでではなくとも、お勧めした書籍についての感想を必ず求めてくる人もいれば、感想は聞かないでも、関連した質問で濁して確認するタイプの人など様々です。
であれば、こちらから、何かの話す機会に「あれ、読みました!」で、こちらから話題を振ってしまったほうが外す事が少ないので、自分から、場を見て話題を振り、その際に書籍も返してしまいましょう。
読んだ記録を残しておくのもポイント
お勧めされた書籍に関する記録をしておくのもポイントです。
筆者の場合、お薦めされた書籍については、公開していない匿名の書評ブログ系のWebサイトを作ってあって、そこに記録してまとめてあります。
Googleアドセンスによる広告収入も付くようにしているので、どうせ読むならと得な感じになると思います。
このあたり、PV数(アクセス数)やCV(コンバージョン)等も気にしなくて良いブログサイトなので、気楽に運用できると考えています。
価値観などの受け取り方に関して
特定の書籍を勧められた場合、人によってはハッキリと受け取らずというような人もいます。
それでも関係性に悪い影響がない場合は良いのですが、筆者の場合、根本には話すのが苦手で対面で話したりすることは得意な方ではないです。
なので、断り方やその理由の伝え方なども不器用なので、薦められた書籍などは基本的に読むようにしています。
ただ、筆者自身の価値観も含め、それぞれの人が持つ価値観は大寿衣にしたい方なので、第三者的に俯瞰して読むようにすることを心がけています。
また、このブログ記事で書いたように、全ての書籍を事細かに覚えておくことはできません。
とはいえ、全く読んでいなければ、書籍を薦めて渡してくれた人と、書籍についての会話をするのに困ってしまうし、そこから得られる、その人の人間性を知るための機会を失っていまう場合があります。
本記事の内容は、慣れると本当に多くの情報を覚えやすくまとめられるようになり。また、書籍数が重なってくると著者も同じ人や、業界、その他にも色々と共通情報が重なって、だんだんと効率も高まってきます。
ぜひ、本記事の進め方で、唐突に、場合によっては無情にも書籍を読むことを責務として受け取ってしまったような場合には試してみてください。
これらの内容がお役に立てば幸いです。