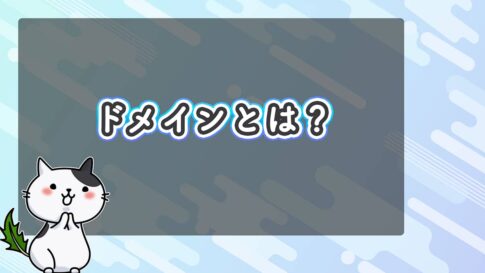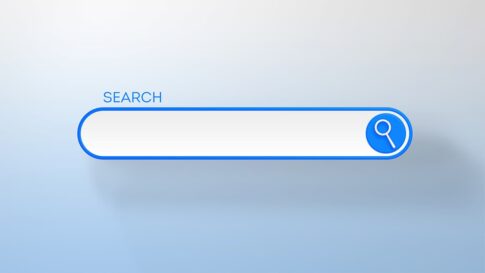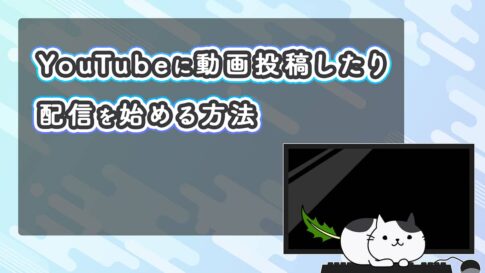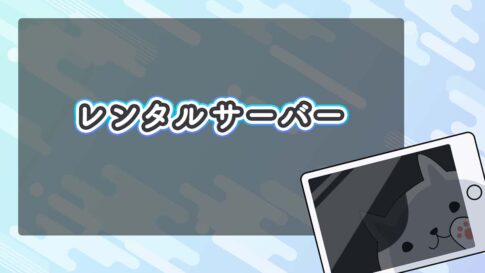基本的にブログサイトの運営では、こう書けば絶対にWebアクセス数は上がる、という鉄板のパターンはありません。
ただ、筆者の場合は公開している運営サイトをいくつかと、匿名で運営しているWebサイトが数十サイトあり、これらはWebサイト丸ごとコンテンツも含めての運営をお願いしているものもあれば、全て筆者自身が書いているブログ型のサイトなどもあります。
ただ、これだけ多くのWebサイトを俯瞰的に見ている*1と、それなりではありますが下記の3つのパターンが見えてきます。
- 共通して成長したパターン
- 成長が止まってしまったパターン
- むしろアクセス数が下がってしまったパターン
など、個人なりに集まった多少なりの定量的なデータがあります。
今回は、その3パターンを簡単に紹介できればと思います。
恐縮ながら、筆者が運営している、このユニコブログ®︎の実績について少しだけ紹介します。
| ブログサイト名 | ユニコブログ®︎ |
| サイト開設日 | 2020年01月 |
| レンタルサーバー | ConoHa WING |
| 利用しているCMS | WordPress |
| WPテーマ | STORK19 |
| 最高月間PV数 | 56.5万PV(2023年01月)|ブログの始め方と人気ブログの作り方を完全初心者向けに解説 より |
| 最高月間収益 | 1,217,403円(2021年05月)|ブログ収益の公開記事 より |
| 収益化の方式 | ASP経由のアフィリエイト広告及び直接広告 |
| 記事数 | ブログ記事数は600記事 |
| 登録商標 | ユニコブログ 登録商標第6335150号 |
このほかに運営しているWebサイトやブログサイトでも、ある程度の実績は出ているのですが、このユニコブログ®︎が開設からの運営期間も1番長くて、実績も大きいので実績公開をさせていただきました。
個人ブログのブログ名や独自ドメイン
これについては、短くて覚えやすいブログ名であれば何でも良いのですが、最近は知らずにブログ名が被ることが多くなったりしてきています。
サイト内で扱う情報が特化されていれば、短くなくても、その情報に関連した特化型のブログ名を書いてしまう形で問題ないです。
けれど、独自ドメインに関して言えば、日本向けであれば、「.jp」で取得しておきたいし、英語であれば「.com」や「.net」。
また、例えば昨今、海外向けの発信コンテンツとして成長が目覚ましい場所として注目されているインドであれば、言語は英語にしてもドメインは「.in」など。
※「.in」等は、WHOIS*2代行にホスティング会社が対応しているか確認が必要です。
特に、日本向けであれば、「.jp」は3文字だけのドメイン名も余っているのでチャンスです。
お名前.comなどで、まだ余っているドメインなどを確認することもできるので検索してみると楽しいです。
個人ブログのブログ記事のタイトル名やキーワード選定について
通常、キーワード選定を行うときは専用のツールを使ったり、検索エンジンが元々実装しているサジェスト、共起語など、単語について色々とこねくりまわして決めていくことが多いのですが、個人ブログに多い、特に趣味によった内容の場合は、キーワードツールから抽出される単語の組み合わせより、「商品の型番そのもの」のほうが、実はキーワードボリュームが多かったりします。
なので、同じ趣味を持ち始めた初心者向けと、商品名、さらには型番名をレビューした記事などが、個人ブログで躍進するための隙間テクニックになります。
個人ブログのカテゴリーの分け方も楽になる
このやりかたでブログ運営していくと、カテゴリーの分け方も楽になります。
雑記は別途分けた上で、該当するテーマのブログ記事は、大分類として、例えば
- 折紙
- 文具
- 家電
中分類に「メーカー名」、小分類にはメーカーが分類している内容合わせて更にカテゴライズしても良いし、小分類まではしないで、「メーカー名」のカテゴリー下に、「型番」をブログ記事の先頭に持ってくるブログ記事タイトルの決め方とする方法で決めてしまうのが良い感じです。
個人ブログで書いていくブログ記事全体の構成について
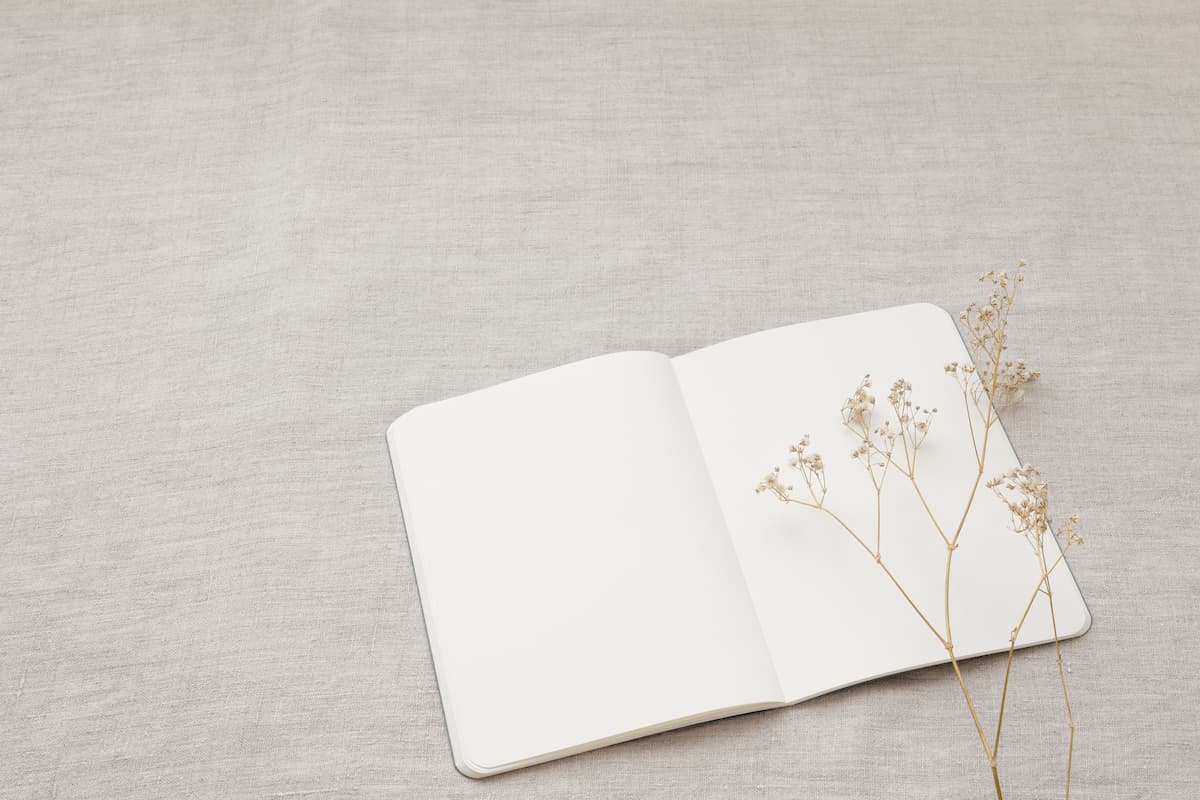
個人ブログのブログ記事構成はシンプルな構成です。
個人ブログのブログ記事に書いていくリード文
その製品(型番)の何をレビューしていくのか、ブログ記事の全体を、淡々と150文字位で書いていきます。
特にその製品と出会った経緯など必要なく、その製品を使うキッカケになった要点だけを書いてしまうのが良い感じになると考えています。
リード文と合わせて、SEOで多少なりとも重要とされているディスクリプション*3に関しても、ブログ記事の本文とは別に、極力少ない文字数でブログ記事の内容を紹介できるようにするようにしたものが、検索結果から選ばれる傾向が高いです。
個人ブログのブログ記事本文
その製品(型番)の仕様などを簡単に書いていきます。テーブルタグで仕様に関する情報を書いていくのも良いのですが、筆者の場合は「見出し」になるHタグで書いていくようにしています。
また、製品名に加えて「型番」などまでの検索クエリでサイトを訪問してくるとなると、その製品の購買意欲は高い状況であることが多いと考えています。
従って、製品や商品レビューを淡々と書いていき、購入したときの利用イメージが明確な文章を、こちらも淡々と書いていくのが良い感じになります。
ブログ記事の本文終わりに書いていくまとめ部分について
文章作成が終わり、ブログ記事によくある「まとめ」の見出し部分まできたら、その「見出し」のタイトルは「まとめ」だけの3文字だけの文章で終わらせ内容にして、下記の様に
「〇〇の製品について●●で補足動画として配信しています」
みたいな感じにして、YouTubeなどの動画配信、または音声配信で発信していることも紹介して導線を作り、それらのコンテンツをブログ記事に埋め込む事ができればベストです。
YouTubeなどの動画配信で顔出しによる配信をする必要はないですし、声などのナレーションについても、今は商用利用が可能なVOICEPEAKのように、多くのAI音声合成ソフトが提供されています。
なので、必要に応じて使い方や使い心地などの動画を、このように匿名性を保ったまま配信や情報発信が可能になっています。
これらのコンテンツ構成は、音声配信による方法でも可能です。
最近だと、
などのプラットフォームが、利用人数が多いので並行してコンテンツを作成していくのがお薦めです。
ブログメディア以外に、できれば1つ、ブログ記事を補足していくための別の情報発信メディアを持っておくと、後々に色んな発信展開を考えて行くことも出来るのでお薦めです。
個人ブログで紹介する商品や製品の広告タグを配置する場所について

個人ブログとはいえ、収益化を目的としている場合も多くあります。
そうすると気になるのが、紹介する広告タグの埋め込み位置です。
最近は、AMAZONアソシエイト等を、素敵な装飾でサポートしてくれるWordPress用のプラグインもいくつかあり、また、テキストベースでリンクをしている方も多くいらっしゃいます。
筆者の場合に限って言えば、広告タグの位置で効果があるのは、ファーストビューよりも少し下*4の1箇所です。
具体的な数字としては、ユーザーがPCの場合、横1920px縦1080pxのフルHDでWebブラウザを表示したときに、バナー、ボタン、テキスト共に、その部分よりも下になるように意識しています。
スマホの場合は、あまりにも種類が多いので、自分がいくつか持っているスマホで表示させてみておかしな所がないか確認する程度にしています。
とはいえ、これが完全に正しい位置かというと、今現状も色々なところで議論が成されているところでもあるので正解とは言えないのですが、現状は、このやり方で上手くいっていると考えているので、全てのサイトで統一して意識する重要なポイントになっています。
ページレイアウトアルゴリズムの改善(英語)|Google検索セントラル
個人ブログで紹介する商品や製品の紹介で使用する画像について
個人ブログで使用する写真や図表などの画像についてですが、もし、可能であれば、ブログ運営者として利用しているアイコンがあれば、そのアイコンイラストやデザインについて、オリジナリティーを高めるためだったり、パクリ防止に役立つ施策があります。
昨今は画像修正の技術が格段に向上されているので、ウォーターマークや透かしなどの加工を加えても、それでもパクられてしまうときはありますが、やらないよりかはというのと、複製防止や著作権侵害防止のために対策を行ったという事実は、後々何かあったときに役立つことになります。
画像や製品などの紹介画像で撮影した画像や図表には、ブログ運営者のアイコンを透かし(50%から70%)のウォーターマークを入れておくと効果的です。
また、予算があればブログ運営者のデザインをキーホルダーやぬいぐるみにして一緒に写真お腹に入れておくのも1つの手法です。
例えば、筆者の場合はクリエイターの方々に制作してもらった色んな1点ものグッズを、撮影する時に添えたりしています。

このほかにも、技術的にユーザーのコピペ感知機能や、画像だけ別サーバーから表示させて画像への何らかのアクションなどを監視したりする方法も技術的にあります。
しかし、費用が膨らむし、気軽にブログ記事を書いていきながら日々監視もしていくには中々重いものがありますので、それらはブログサイトが育ってある程度の予算ができてからでも良いと考えています。
個人ブログは匿名でも大丈夫?

筆者の場合、最初は運営しているブログサイトの公開をしていましたが、最近開設したWebメディアやブログサイトでは、実名ではなく匿名で運用するようにしています。
これについては
- 将来、専門職として実名のブログサイトを運営する予定がある
- 法律上、運営者の明記が必ず必要
というように、実名で運営するメリットが明らかでない限りは、実名表記で運用する必要は全くないと考えています。
正直、最初から匿名で運営していれば良かったと思うWebサイトがたくさんありました。
特定商取引法とは|消費者庁(特定商取引法ガイド)
個人ブログでも収益化が出来る方法はたくさんある

今回紹介した個人ブログでも大きくWebサイト(ブログサイト)を成長させる以外にも、まだまだ多くの方法があります。
ジャンルによっては違うやり方のほうがより効率が良いパターンも多く存在しています。
一例では、海外向けの個人ブログで情報発信していく方法などがあります。
今はDeepl翻訳などの高機能な翻訳Webツールがあるので、日本語の単語が、そのまま英語の単語になった分野などは、まだまだ参入できる余地が多く残されています。
個人ブログで海外に向けての発信ジャンルは多い
人によっては、日本で情報発信するよりも海外向けに発信できる情報や専門性を持たれている方が多くいらっしゃると考えているので、大きくWebサイトを成長させる機会がすぐ側にあると考えています。
海外発信向けのWebサイトでも、日本で提供されているレンタルサーバーサービスで十分に発信環境は整うのでチャレンジする価値は有りと考えています。
これらを進めていく上で、ユニコブログ®及び、本記事がお役に立てば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
個人ブログの成長に関する脚注一覧
- 意見が分かれるところでもありますが、筆者の場合は良くも悪くもに1アカウントでGoogle Search Consoleに全てのWebサイトを登録して管理しています。 ↩︎
- WHOISとはドメインの所有者を検索して調べる仕組みのことを指します。 ↩︎
- メタ ディスクリプション タグを使用する|Google検索セントラル ↩︎
- ファーストビューとはユーザーがスクロール等をせずに、最初に閲覧する画面範囲の事をいいます。ユーザーの利用環境によって、その範囲は大きく変わります。 ↩︎